年長である子供の学習の仕方について、
基本的な考え方、国語の学び方、算数の学び方、英語の学び方、それぞれについて整理していきます。
この記事では、算数の学び方を記載します。
5歳になったタイミングから公文教材進めています。
年長の今までやっていく中で、大事だと思うことと、当面の考え方を整理します。
①算数の構造
基本的には国語と同様で、
算数の構造をきちんと理解した上で、今やるべきことをクリアにして進めていくことが大事です。
ここで記載の構造は、現時点の仮説ですが、
算数力はピラミッド構造で積み重ねになっていると感じています。
当面は1階層目ですね。
(国語と異なるのが、1階層目に時間がかかりそうなのと、
1階層目ができない状態で2階層目にはいきづらいこと)
1階層目:足し算 、引き算、掛け算、割り算(いわゆる四則演算)
2階層目:図形、比・割合、速さ、特殊算といった個別トピック
3階層目:読解力(論理を読み取る力)、表現力・言語化力(組み合わせる力)
2024年9月25日現在、私の子供は足し算は90%程度完了し、
週1回程度忘れないように復習しています。
引き算については現在進捗中で60-70%ぐらいの状況です。
引き算が90%程度までいけば復習を中心にしつつ、掛け算に進んでいきます。
とはいえ掛け算は、九九の暗記になると思います。
なお、100%は目指さないです。
小学校に入れば何度も復習できますし、90%から100%を目指す労力は時間の浪費と考えています。
②使用教材
公文教材を使用しています。5歳開始時点の状況をみて、以下の教材を順番に実施してきました。
足し算については、幼児教材が終了したので、小学校1年生の教材にスライドしたのですが、
2桁の大きい足し算(例:60+30)が理解できないようで、ここでストップしています。
脳の成長を待ちながらタイミングみて再チャレンジ。
引き算については、もう少しで幼児教材が終了するため、その後、小学校1年生の教材にスライドします。
おそらく足し算同様、途中で進まなくなると思うので、その際はできることを復習しつつ、
掛け算(九九)の暗記に入っていきます。
足し算:
はじめてのたしざん→たしざんおけいこ1集→たしざんおけいこ2集→1年生たしざん(今ここ!)
引き算:
はじめてのひきざん→ひきざんおけいこ(今ここ!)
③使用方法
くもんの教材は、裁断しやすいため、裁断してコピー機でスキャンしています。
各教材は3回ほど回しています。今のところ3回やれば90%まで到達しています。
3回回すのにかかる期間はおよそ2か月です。
なお、1日あたりの学習時間は約15分~20分程度です(子供のやる気でだいぶ変動します・・・)
1回目:
裁断した原本を使って、1日に両面1枚から2枚を実施。
1枚にするか2枚にするかはボリュームで都度判断。
2回目:
スキャンデータを印刷して、1日に両面1枚から2枚を実施。
1枚にするか2枚にするかはボリュームで都度判断。
国語と異なり、2in1設定にすると、字が小さく、数字が大量になって嫌気がさすため、
1in1両面としています。つまり1回目と同様。
3回目:
2回目と同様。
2回目までに苦手な計算パターンがでてくるので(例:8+9)、苦手な箇所を意識して丁寧に取り組んでもらう。
その際は一声かけながら(”ここ集中!”、みたいな)、計算してもらっていました。
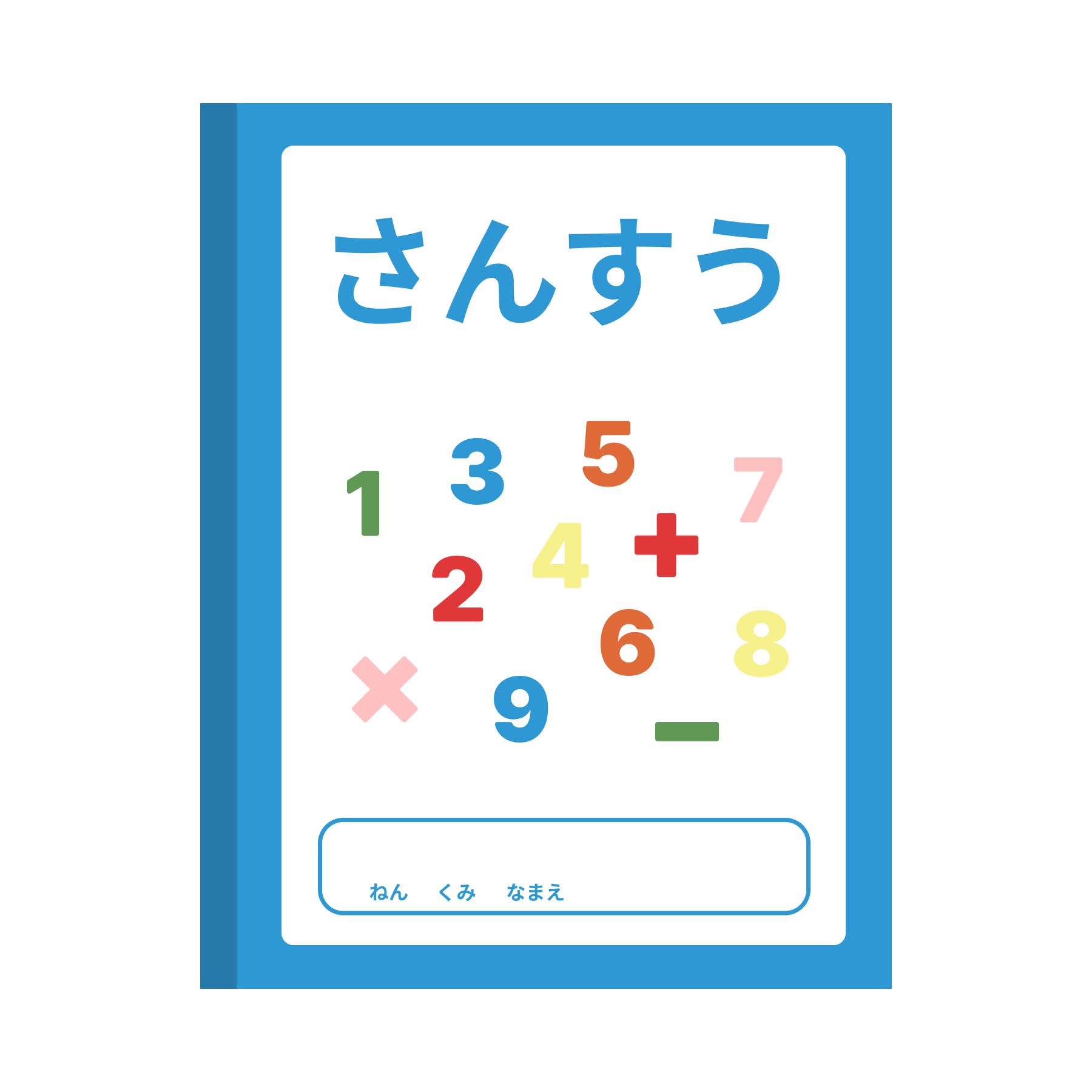


コメント